


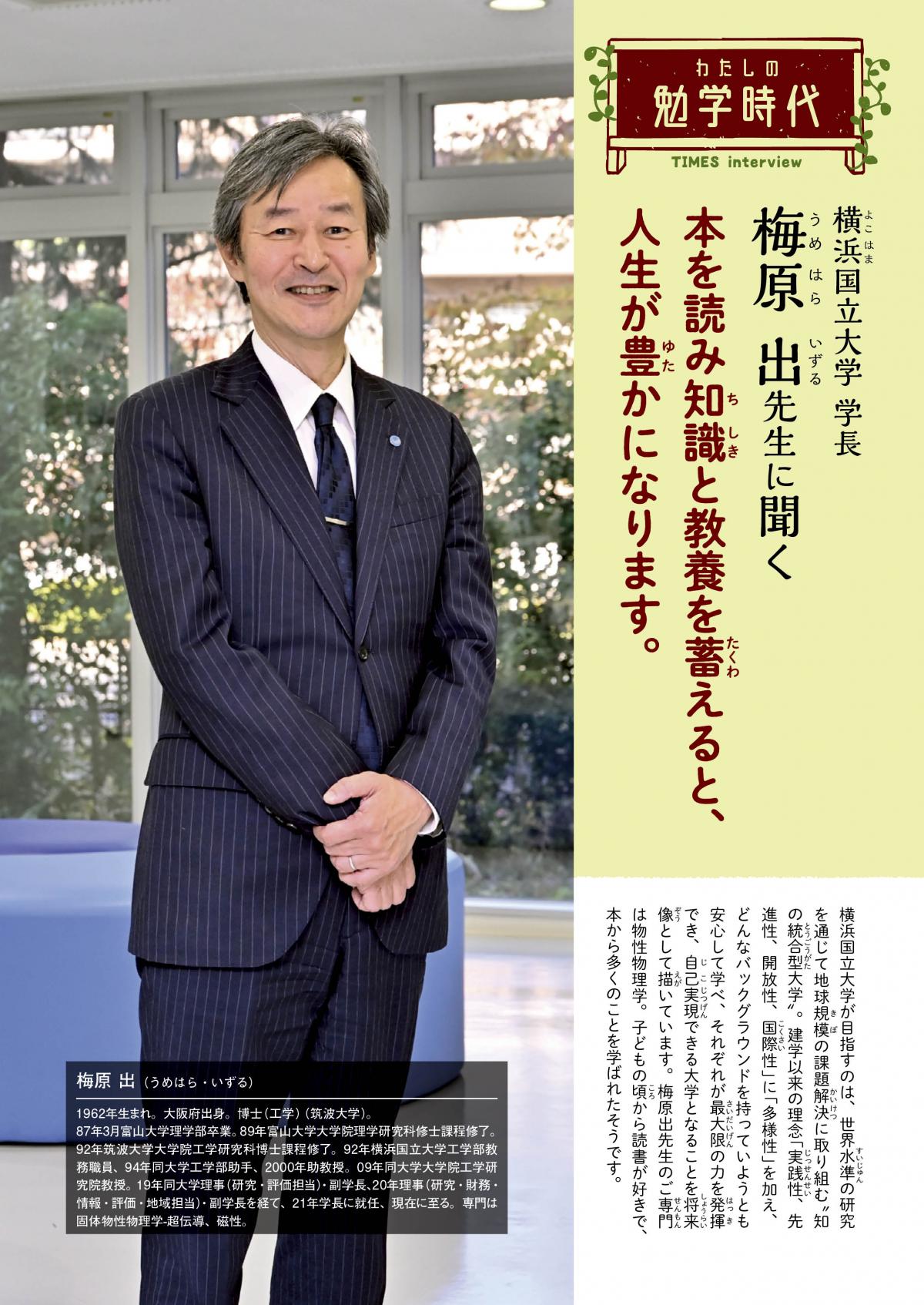
横浜国立大学が目指すのは、世界水準の研究を通じて地球規模の課題解決に取り組む“知の統合型大学”。建学以来の理念「実践性、先進性、開放性、国際性」に「多様性」を加え、どんなバックグラウンドを持っていようとも安心して学べ、それぞれが最大限の力を発揮でき、自己実現できる大学となることを将来像として描いています。梅原出先生のご専門は物性物理学。子どもの頃から読書が好きで、本から多くのことを学ばれたそうです。
【梅原 出 (うめはら・いずる)】
1962年生まれ。大阪府出身。博士(工学)(筑波大学)。
87年3月富山大学理学部卒業。89年富山大学大学院理学研究科修士課程修了。92年筑波大学大学院工学研究科博士課程修了。92年横浜国立大学工学部教務職員、94年同大学工学部助手、2000年助教授。09年同大学大学院工学研究院教授。19年同大学理事(研究・評価担当)・副学長、20年理事(研究・財務・情報・評価・地域担当)・副学長を経て、21年学長に就任、現在に至る。専門は固体物性物理学-超伝導、磁性。
生まれたのは大阪府藤井寺市、育ったのは富田林市です。藤井寺市は、当時あったプロ野球球団・近鉄バファローズの本拠地で、そのホームグラウンドの藤井寺球場は自宅から電車で10分ほどのところにありました。母方の祖父が藤井寺駅の駅長で球場管理の仕事もしており、チケットをもらって父とよく野球観戦に行きました。もちろん大の近鉄ファン……ではなく、父も私も*1阪急ブレーブスファン(笑)。好きな選手はアニメ『巨人の星』の主人公・星飛雄馬で、所属していた草野球チームではピッチャー……と、この頃は野球に熱中していました。
父は中学校の英語教師、母は専業主婦で、家でのしつけや勉強は父の方が厳格でした。「勉強しなさい」とは言わなかったものの、「お前は何のために生まれてきたんだ。人類のためだろう。だから勉強は大切なんだ」と、物心つく頃から繰り返し言い聞かされました。
好きだった教科は国語や社会。本が好きになったのは間違いなく読書家の父の影響です。本に囲まれて暮らしていたと言ってもいいほど、家にはジャンルを問わず、いろいろな本がありました。よく買ってもらったのは偉人の伝記ですが、どんなものでも片っ端から読んでいましたね。
*1 現在のオリックス・バファローズの前身球団。
▲子どもの頃の遊びはもっぱら草野球。私が小学生だった昭和40年代は、巨人の長嶋選手や王選手がヒーロー。男の子はみんな野球好きという時代でした。
中学は地元の公立校へ。小学生の頃から足の速さには自信があったので陸上部に入りました。中長距離走の選手として部活に打ち込み、地区大会では常に1、2位を争う成績を収めていました。
中学校の時の成績は、定期テストで散々な点数をとることはなく、かと言って飛び抜けて良い点数をとることもなく、3年間いたって普通でした。数学は幾何が好きだったのですが、なぜかというと非常に論理的だからです。問題が解けた時に「やったぞ!」という達成感、充足感を味わえるのが楽しかったですね。
中学時代を振り返ると、授業のことはあまり記憶にありませんが、やはり本をたくさん読んでいたことは覚えています。この頃は歴史小説にはまり、司馬遼太郎や吉川英治などの読み応えのある分厚い本を次々に読破していました。
高校は父のすすめで私立の桃山学院高校に進学。受験前には入試教科の国語・英語・数学を重点的に勉強しました。
▲受験勉強は、点数をとるためのテクニックより基礎に重点を置いていました。基礎をしっかりやっておくことが、定期テストでも受験でも一番大切ですよ。
高校生になると音楽や映画の楽しさに目覚め、かなりのめり込んだ時期もあります。この頃にユニークな物理の先生に出会ったことが大きな転機になりました。他の先生は教科書に沿って教えるのに、この先生は教科書に書かれていない哲学的な物理学や思想的な部分も教えてくれたのです。「運動方程式を使えば世界のすべてのことが理解できる」とまで断言されていて、その言葉に感銘を受けた私は物理学の道に進もうと決めました。この先生との出会いがなければ、物理とは全く違う方向に進んでいたかもしれません。
富山大学を志望した理由は単純明快。ふと目にした受験雑誌に、素粒子理論で有名な松本賢一先生が富山大学に在籍していると書かれていたからです。「松本の質量公式」を発見された先生で、「公式を見つけるなんてすごい。これはもう行くしかない!」と。当時の私は、物質とは何か、質量とは何かという根源的なテーマを掘り下げる物理学に憧れを抱いていて、松本先生の研究室ではそれを追究できるだろうと考えたのです。「絶対に松本先生の研究室に入るんだ!」という一心で受験勉強に励み、富山大学理学部への入学を果たしました。
晴れてスタートした大学生活。ある日、キャンパスで何やら独り言をつぶやきながら歩く個性的な人がいました。その人こそ憧れていた松本先生でした。量子力学の講義では“鉄腕”をふるってお書きになった数式でいっぱいの黒板を見て“ちょっと違うかも”と思い始めて……。まだまだ幼かったのでしょう。高校時代の物理の先生のようにワクワクさせてくれる講義を期待していた私は、憧れから一転、「素粒子理論の研究室はやめておこう」という結論に至りました。
そんな中、物性物理学を専門にしたのは、物性物理序論の講義で超伝導現象を教授に見せてもらったことがきっかけです。*2マイスナー効果を目の当たりにしてたちまち興味を惹かれ、3年の終わりから研究室に入り、学部卒業後は大学院に進みました。
私が研究したのは、電子同士が反発する相関が織りなす「重い電子系の物理」。かなり特殊だったこの研究を続けたいと思っていた矢先、予期せぬ来訪者がありました。この分野の新進気鋭の研究者で、筑波大学で教えておられた大貫惇睦先生がわざわざ会いに来てくださったのです。研究を紹介すると、「ぜひ私のところに来なさい」。そうして筑波大学大学院に入り、博士課程を修めることができました。
当時はとにかく実験と研究に明け暮れる毎日。実験装置そのものを一から作ることも当たり前で、いざ実験を始めても今のように自動化されていなかったので、学生がまさに“朝から朝”まで張りついていなければなりませんでした。何日も続けてあれほど寝なかったのは、後にも先にもこの時期だけですね(笑)。
*2 超伝導体の内部に磁場が侵入できなくなる現象。超伝導体の上に磁石を乗せると、重い磁石は下に落ちず、重力に逆らうように浮く状態になる。
望まれたところで仕事をしたい――そう思い続けています。横浜国立大学には教務職員として入職し、当初は研究に専念できない環境でした。それでも請われて来たという思いが強く、教務の仕事に真摯に向き合い懸命に取り組みました。だからこそ今があるのかなと思いますね。国立大学の学長で教務職員からキャリアをスタートしたのは、私だけかもしれません。大学運営に携わる立場となった今、事務方と一緒に仕事をするという経験をしたことがとても役に立っています。
学長の就任に際しても、まわりに望まれて立候補に至りました。副学長時代から国立大学を取り巻く状況に危機感を持っていて、このままではふるい落とされてしまう、研究職を捨ててでも大学のために力を尽くさなければ、と決意を固めました。
そして学長就任後に掲げたのが「“知の統合型大学”として、世界水準の研究大学を目指す」というビジョンです。世界水準とは、世界の大学ランキングの上位を目指すという意味ではなく、地球規模の問題や課題に正面から挑める教育・研究機関としての大学に発展させるということです。さらに、ダイバーシティ(多様性)を重視し、性別、障がい、国籍などを超えて、一人一人が豊かにその力を発揮できる環境を整えることも始めています。
皆さんがいろいろなことを学び、好きな学問をもっと深めたいと思った時、様々な領域の知識を幅広く持ち合わせていれば、学びはさらに充実したものになるでしょう。その源泉になるのが“本”です。知識や教養は自分自身を成長させる血肉となるもの。私自身、豊富な読書経験が多彩な価値観と感性を育ててくれたと感じています。皆さんもぜひ、本をたくさん読んで、豊かな人生を送ってください。
SEARCH
CATEGORY
よく読まれている記事
KEYWORD