


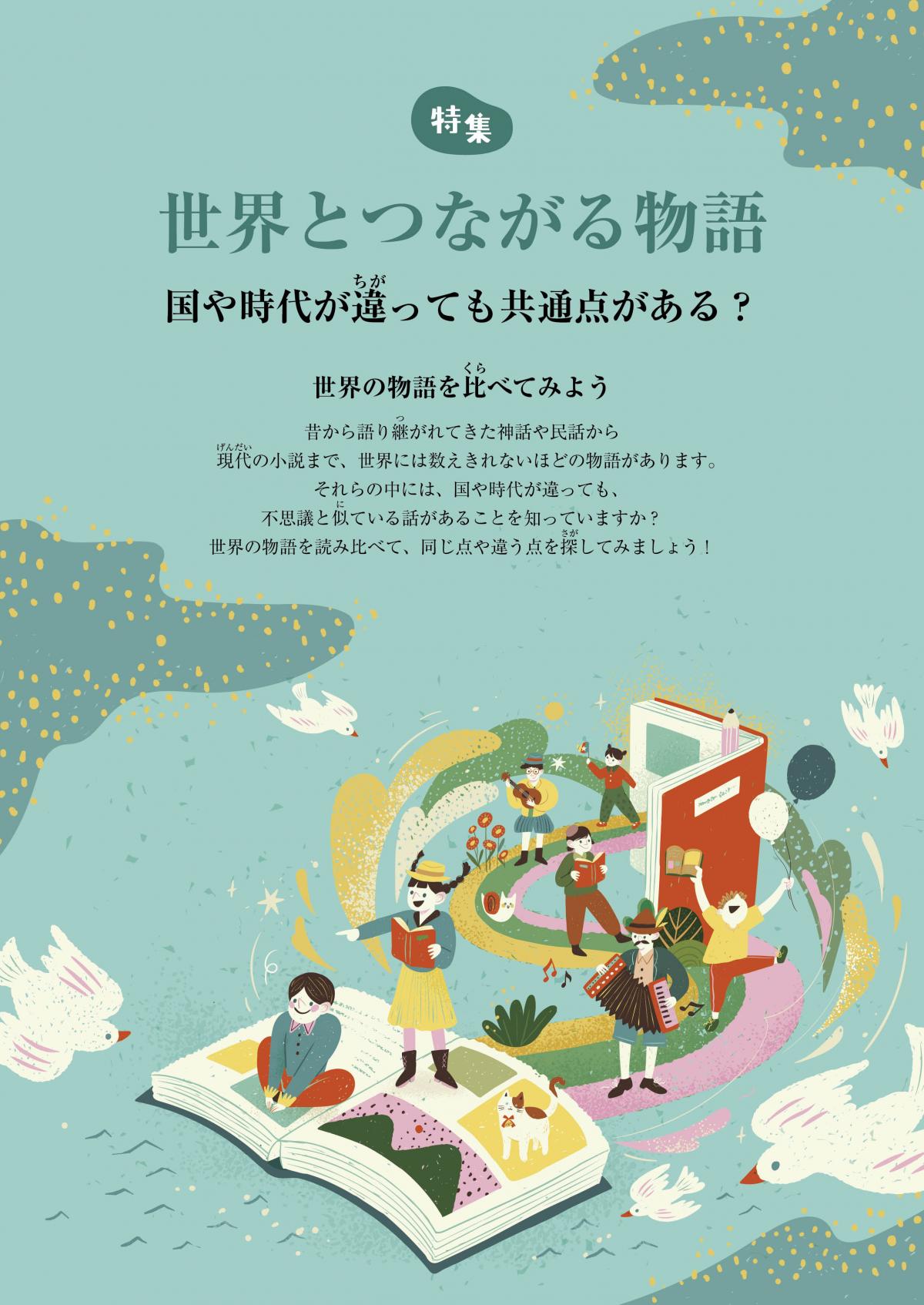
昔から語り継がれてきた神話や民話から現代の小説まで、世界には数えきれないほどの物語があります。それらの中には、国や時代が違っても、不思議と似ている話があることを知っていますか? 世界の物語を読み比べて、同じ点や違う点を探してみましょう!
世界や人類がどのように誕生したのかを説明する物語は世界中にあります。その多くは、神によってつくられたとするものです。いろいろな世界の始まりを見ていきましょう。
夫婦神イザナギとイザナミが天地の間にかかった天浮橋から矛で海をかき混ぜて引き上げると、矛からしたたり落ちた塩水が積もって島となった。二神は島に降り立ち、淡路島、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐渡と次々と島を生み、最後に本州を生んだ。次に、石の神、土の神、海の神、風の神、山の神、穀物の神とあらゆる神々を生んだが、火の神を生んだことでイザナミが死んでしまった。

▲小林永濯筆『天之瓊矛を以て滄海を探るの図』(ボストン美術館蔵)
天地ができるより前、世界は卵の形をしていた。陰と陽が混ざり合って混沌としていた中に、盤古という巨人が生まれた。盤古は卵を割り、背丈を伸ばして少しずつ世界を押し広げ、1万8千年かけて天と地を分けた。盤古が死ぬと、その息は風や雲になり、声は雷となり、左目は太陽に、右目は月となった。体は山や地に、血液は海や川に、髪や毛は草木に、汗は雨になった。
最初にカオス(混沌の神)があり、ガイア(大地の神)、タルタロス(冥界の神)、エロス(愛の神)が生まれた。カオスから、エレボス(闇の神)、ニュクス(夜の神)が生まれ、エレボスとニュクスから、アイテル(光の神)、ヘメラ(昼の神)が生まれた。ガイアから、ウラノス(天の神)、ウーレア(山の神)、ポントス(海の神)が生まれた。ガイアとウラノスから様々な神々や巨人が生まれた。
最初は、太陽神アトゥム・ラーだけがいた。ラーは、口から大気の神シュウと湿気の神テフヌトを吐き出した。シュウとテフヌトから大地の神ゲブと天空の神ヌトが生まれた。ゲブとヌトは抱き合っていたが、シュウが二人を引き離し、ヌトを天高く持ち上げ、ゲブは大地に横たわらせた。ゲブとヌトの間に、冥界の神オシリス、豊穣の神イシス、葬祭の神ネフティス、戦争の神セトが生まれた。
神々と悪魔たちが、不死の薬アムリタを求めて争っていた。世界を維持する神であるヴィシュヌ神が「争いを止め、協力して大海をかき回せば得られる」と言った。そこで、海の中にマンダラ山を置いて軸棒とし、亀の王の背中で支え、大蛇を巻きつけた。大蛇の尾を神々が、頭を悪魔たちがつかんで海をかき回すと、海はやがて乳の海となった。そこからヴィシュヌ神の妃ラクシュミー、神の酒、太陽、月、宝石、家畜、白馬などが次々と現れ、最後にアムリタの入った壷を持った医の神が出現した。

▲乳海攪拌のモニュメント(タイ・スワンナプーム国際空港)
最初に混沌があった。神が6日間かけて世界をつくった。1日目、神が「光あれ」と言うと光がさし、光と闇、昼と夜に分かれた。2日目、水が上と下に分けられ、上が天になった。3日目、下の水が海になり、大地がつくられた。4日目に太陽と月と星、5日目に水中の生き物と鳥がつくられた。6日目に地上の生き物、最後に神に似せて人がつくられた。7日目、すべてをつくり終えた神は休んだ。
昔話や民話は、人から人へと語り伝えられてきた身近な話です。同じような型の話が世界中にあることが知られています。いくつか読み比べてみましょう。
神や精霊、動物など、人以外の相手と結婚する話を「異類婚姻譚」と言い、世界中に存在しています。結婚後、正体がばれたあとの結末にはいくつかの異なるパターンがあります。
日本「鶴女房」
昔、貧しいが心の優しい青年がいた。ある日、一羽の鶴が罠にかかってもがいているところに通りかかり、鶴を助けてやった。翌日、美しい娘が青年の家を訪ねてきて「嫁にしてほしい」と言う。青年に嫁いだ娘は、「これから布を織りますが、決して中を見ないでください」と部屋に籠って布を織り始めた。7日後に織り上がった反物は高く売れた。娘はもう一反織り始め、青年は「糸もないのにどうやってあんな美しい布を織るのだろう」と気になって我慢ができず、ある日、約束を破って部屋の中を覗いてしまった。そこでは一羽の鶴が自分の羽根を抜いて反物を織っていた。鶴は、「私はあなたに助けられた鶴です。姿を見られたからにはもうおそばにいられません」と言い残し、飛び去っていった。
中国「白蛇伝」
千年の修行を経て美女の姿となった白蛇が、侍女に姿を変えた青蛇とともに人間の世界を訪れ、薬売りの青年に一目惚れした。二人は結婚して、幸せな日々を送ったが、強い神通力を持つ僧侶が白蛇の正体に気づき、正体を暴こうとする。青年は信じなかったが、妻に酒を飲ませると、白蛇の姿に変わった。衝撃を受けて倒れてしまった青年を、白蛇は薬を手に入れて救った。しかし、僧侶が青年を寺に閉じ込め、その間に白蛇を退治しようする。白蛇は僧侶との戦いに敗れ、塔に捕らえられてしまったが、侍女の青蛇が法術で救い出す。夫婦は無事に再会し、子どもたちと一緒に楽しく暮らした。
フランス「バラ(蛙の婿)」
商人が町へ買い物に出かける時、3人の娘たちのうち、末娘が「きれいなバラの花」を土産にほしがった。父親は町でバラを見つけられず、帰り道、森で道に迷って城にたどりつく。城には誰もいなかったが、謎の声に導かれて一晩休んだ。翌朝、帰る際に、商人は庭に咲いていたバラを末娘のために手折る。すると、恐ろしい声が聞こえ、末娘をよこすように約束させられた。話を聞いた末娘は自ら城へ行く。城には誰もいなかったが、ごちそうがあり、寝室も整えられていた。娘は数日一人で過ごしたが、ある日、醜いヒキガエルが現れ、結婚してほしいと言った。娘が拒絶すると、ヒキガエルは姿を消した。探しに行くと、ヒキガエルは沼の中で悲しそうに泣いていた。心を痛めた娘が求婚を承諾すると、ヒキガエルの呪いが解け、美しい王子が娘の前に現れた。

出会った人との持ちもの交換をきっかけに話が展開します。良いものに交換していくパターンと、悪いものに交換していくパターンのどちらも存在しています。
日本「わらしべ長者」
運のない貧しい男が、観音に運を与えてほしいと願う。すると観音が現れ、お堂を出て初めて手にした物を大切にして西へ行くようにと言われた。男は転んで一本の藁を手にした。藁を持って西へ行くとアブが飛んできたので、藁でしばって進んだ。子どもがほしがったのであげると、母親がお礼に蜜柑をくれた。水をほしがって苦しんでいた娘に蜜柑をあげると、代わりに上等な絹の反物をくれた。倒れた馬と荷物を取り換えてくれと侍に言われ、馬を強引に引き取らされてしまったが、男が馬を介抱すると元気になった。馬を連れて進むと、長者が千両で買うと言った。その長者の娘は蜜柑をあげた娘だった。男はその娘と結婚し、大長者になった。

ドイツ「運の良いハンス」
7年間真面目に働いたハンスが、頭ほどの大きさの金の塊をもらって故郷に帰ることになった。金塊を持ち歩くのが重く感じ始めた時、騎士に出会い、馬と交換した。しかし馬に投げ出され、百姓の雌牛と交換した。乳を搾ろうとしても出なかったので、肉屋の子豚と交換した。ガチョウを抱えた男に、近くで子豚が盗まれたから犯人と勘違いされてしまうと言われ、ガチョウと交換した。研ぎ屋の男に出会い、良い仕事になると言われて砥石(重い石)と交換した。重い石を運ぶのに疲れて、井戸のへりに置いて水を飲もうとした時、石が井戸の底へと落ちてしまった。ハンスは、運良く神様が自分を石の重荷から解放してくれた、と感謝した。
昔の物語だけではなく、小説や漫画など、現代の作品にも通じるものがたくさんあります。今の物語も比べてみましょう。
2024年に刊行されて話題になった『物語要素事典』は、古今東西のあらゆる物語を核となるアイデア=物語要素ごとに分類してあらすじを紹介する事典です。文学だけではなく、漫画や映画、演劇など、幅広いジャンルの作品が対象になっています。
例えば「旅」の項目を見ると、「主人公たちが果てしない旅をする」「神が身をやつして旅をする」「異界への旅」「旅する動物・異類」など、さらに細かい項目に分け、作品が紹介されています。このうち「異界への旅」には、例として次の5つの作品が挙げられています。『銀河鉄道999』(松本零士著/漫画/1977~81年)、『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著/小説/1934年)、『2001年宇宙の旅』(スタンリー・キューブリック監督/映画/1968年)、『星の王子さま』(サン=テグジュペリ著/小説/1943年)、『*本当の話』(ルキアノス著/小説/167年頃)。
これらの例を見ると、新しい発想に思えるようなものも、昔の物語からつながっていることがわかります。皆さんも、自分が楽しんでいる作品に似ているものがないか、探してみましょう。
*2世紀のギリシャの作家ルキアノスによって書かれた小説。奇想天外な発想による冒険譚で、『ガリバー旅行記』(スウィフト著/18世紀)などに大きな影響を与えた。
SEARCH
CATEGORY
よく読まれている記事
KEYWORD